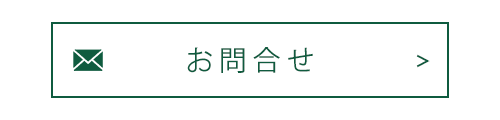Q&A
牛について
| Q1 | 牛の品種は、どんなものがいますか? |
| A1 | 牛の品種には、牛乳を搾るための牛と、牛肉になるための牛がいます。牛乳を出すための牛はホルスタイン種が日本ではメジャーで、味が濃いジャージー種もいます。 牛肉になるための牛は黒毛和種が有名ですが、他にも短角種・無角和種・褐毛和種等がいます。 また、その他には、ホルスタイン種を母牛にして、黒毛和種等の肉用種と交配した交雑種(F1)もいます |
| Q2 | 交雑種(F1)ってどんな特徴がありますか? |
| A2 | 交雑種(F1)とは、 一代雑種牛(Filial 1 hybrid)の略称で、異なる品種の牛を交配して生まれた1代目の牛のことをいいます。F1(交雑種)の牛に、また別の品種の牛を交配するとF2、さらにF2に他の品種を交配するとF3、F4…とります。 なぜ、ホルスタイン種等の乳用種の母牛に、黒毛和種等の肉用種を交配するかというと、大きくな理由が2つあります。1つ目は、体の大きい乳用種と美味しい肉質の肉用種を交配する事で、乳用種から牛肉を生産するよりも美味しい牛肉を生産することができます。2つ目は、乳用種に子牛を生ませるためです。子牛が生まれることで、乳用種が牛乳を出し、出荷することができるからです。他にも理由がありますが大きくはこの2つになります。 |

| Q3 | 乳用種が出す1日あたりの牛乳の量はどのぐらいですか? |
| A3 | 乳用種の牛乳の量(泌乳量)は、出産からどれくらい経っているかで、変わります。ホルスタイン種の場合、出産(分娩)直後は、1日あたり20ℓほどですが、分娩後2カ月ほどで最も多くなり、1日あたり30~50L、それ以上を泌乳する牛もいます。1回の出産で搾乳期間は280日~330日程度で、1頭あたり平均8,500ℓの牛乳を生産します。 また、遺伝的な品種改良を重ね、乳用種の泌乳量は、年々増加しています。 |
| Q4 | 肉用牛は、どのぐらいの期間で肉として出荷されますか? |
| A4 | 宮城県では、黒毛和種の場合、生まれてから30ヶ月ほどで出荷されます。他県では、24か月で出荷する場合もあり、県や銘柄によって違います。 |
| Q5 | 牛を飼う農家は、どのような経営をしていますか? |
| A5 | 代表的なものをあげると、乳用種を飼って搾乳を主とする経営をしている「酪農家」。 肉用種の農家は主に3種類の経営に分かれています。1つ目が、繁殖用の母牛を飼 育し、種付けから分娩、そして生まれた子牛を10か月程度飼養し、子牛市場に出荷する「繁殖農家」。2つ目が、子牛市場に出荷された子牛を購入し、肉を生産することを目的に出荷するまで飼養(これを肥育(ひいく)といいます)する「肥育農家」。3つ目が、自身の農場で生まれた子牛を肥育する「一貫農家」などがあります。 その他にも、いろんな経営をしている農家があります。 |
| Q6 | 牛肉に表示されている「A5」や「B5」の意味はなんですか? |
| A6 | 公益社団法人 日本食肉格付協会が定めた全国統一基準の枝肉取引規格に基づいて、枝肉を格付け(ランク付け)します。牛肉は、「歩留等級」の3区分と「肉質等級」の5区分の組み合わせにより計15の等級にわかれます。 歩留等級とは、牛肉の歩留まりがどの程度あるかで決まります。歩留等級の表示はアルファベットで表記され、上からA・B・Cとなります。肉質等級とは、牛肉の中にある脂肪の入り具合(霜降り)や肉色、肉のしまりや、脂肪の質などで決まり、表示は数字で表記され、上から5・4・3・2・1というランクに分かれます。 「A5」は、その格付けの中でも最高の評価(格付)を受けた証となります。 |
| Q7 | 「仙台牛」と「仙台黒毛和牛」の違いはなんですか? |
| A7 | 「仙台牛」も「仙台黒毛和牛」も同じ肉専用種の黒毛和種ですが、「仙台牛」はQ6にある格付で、「A5」または「B5」となり、指定された農家によって肥育された牛のみとなります。有名銘柄牛の中でも、肉質等級を5等級に限定しているものは他にはありません。 また、「仙台黒毛和牛」はQ6にある規格「A4」~「A3」、「B4」~「B3」、「C5」の格付けで、「仙台牛」と同じく指定された農家によって肥育された牛のみとなります。 |
| Q8 | 牛にも血統書みたいなのはありますか? |
| A8 | あります。 乳用種は、ホルスタイン種、ジャージー種それぞれで登録書があります。昔は、ホルスタイン種の登録書には、1頭ごとに模様が違うため、模様を記入した登録書が発行されていました。現在の登録書に模様は記載されていません。 肉用種では、黒毛和種や他の品種でもそれぞれ純粋種の子牛登記書など複数種あります。黒毛和種の子牛登記書には、人の指紋に当たる鼻紋(びもん(鼻の模様))を現在でも記載しています。 |
| Q9 | 牛の耳についている黄色いイヤリングのようなものはなんですか? |
| A9 | 耳標(じひょう)と言います。この黄色の耳標は、10桁の番号が記されており、生まれた時に牛の両耳に付けて、牛肉になるまで外すことはありません。また、耳標がない牛は、出荷や流通する事ができません。もし、耳標が外れた場合は、飼養している農家は、同じ番号で再装着します。 Q8にある登録書には、この耳標に記されている10桁の番号が記載されています。 |
| Q10 | 牛肉のパックに記載されている「個体識別番号」って何ですか? |
| A10 | Q9にあった耳標に記載された10桁の数字を「個体識別番号」と言います。この「個体識別番号」は、平成13年に日本で発症したBSE(牛海綿状脳症)がきっかけで実施されたもので、牛の品種や生年月日、どこで飼養されたのかなど牛の一生を確認することができるものです。これは、平成15年に制定された「牛トレーサビリティ法」に基づくもので、牛の戸籍のようなものです。 ちなみに、「個体識別番号」は、誰でも検索することができます。独立行政法人家畜改良センターのHP等から検索することができます。ぜひ検索をしてみてください。 |
豚について
| Q1 | 豚の品種は、どんなものがいますか? |
| A1 | 豚の品種は、白い豚では大ヨークシャー種(略称:W)、中ヨークシャー種(略称:Y)、ランドレース種(略称:L)がいます。黒い豚はバークシャー種(略称:B)、ハンプシャー種(略称:H)、茶色の豚はデュロック種(略称:D)がいます。 それぞれの品種で、異なった特徴をもっており、例えば白い豚でも、大ヨークシャー種は体が大きく耳は立っている豚で、ランドレース種は顔を覆うぐらい大きい耳をしています。 |
| Q2 | 「三元豚」とは、何ですか? |
| A2 | 「三元豚」とは、3つの品種を交配したことに生まれた豚です。日本の多くの「三元豚」は、ランドレース種(L)と大ヨークシャー種(W)を交配して生まれた豚(LW)に、デュロック種(D)を交配して生まれた豚のことです。 これは、産子数が多く繁殖性に優れた豚に、発育速度が速い豚、肉質の良い豚と交配することで、それぞれの良い所が持ち合わせた豚を作ることにより生まれたものです |

| Q3 | 豚は生まれてからどのぐらいで肉になるのですか? |
| A3 | 豚は、生まれて6か月程度で豚肉となります。生後1ヶ月ほどで、母豚から引離 され、2ヶ月間は粉ミルクや子豚用の餌で飼養します。体重が約50㎏になったころから大人用の餌に変え、約120㎏で出荷し、豚肉となります。 |
| Q4 | 豚肉に格付けはないのですか? |
| A4 | 公益社団法人 日本食肉格付協会が定めた全国統一基準の枝肉取引規格に基づいて、枝肉を格付け(ランク付け)します。豚肉にも牛肉ほど細かくはありませんが、「極上」「上」「中」「並」「等外」の5つに分けられます。 また、豚肉はサシ(脂肪交雑)が入りにくいなど、牛肉とは特性が違うため、検査項目も異なります。主に重要視されるのは、枝肉重量と背脂肪の厚さとなっています。 |
| Q5 | 豚肉はなぜ生で食べてはいけないのですか? |
| A5 | 豚肉は牛肉と異なり、肉の内部にも菌やウイルスがあります。豚肉を生で食べると、E型肝炎ウイルスの感染や、サルモネラ属菌などによる食中毒、有鉤条虫などの寄生虫の感染リスクがあります。そのため、しっかり中まで火を通してから食べる必要があります。 また、牛肉でも加工や調理過程で肉表面や内臓などの菌やウイルスが付着している可能性もあるため、生食は禁止されています。一部のサイコロステーキなどは切った肉を成形しサイコロ状にしているため、肉の内部に菌等が付着している場合があり、しっかり中まで火を通して食べる必要があります。 |
| Q6 | 豚にも血統書みたいなのはありますか? |
| A6 | あります。 一般社団法人日本養豚協会で発行している血統登録証明書という証明書があります。 |
| Q7 | 豚は、一回に何頭生むのですか? |
| A7 | 品種によって異なりますが、平均すると12頭前後分娩します。豚のおっぱいは、2列の7個、計14個のおっぱいが最大あります。そのため、12頭生まれても授乳することが可能です。 また、子豚は、一度、授乳したおっぱいの場所を覚えて、ずっとそのおっぱいのみを吸うようになります。 |